薬剤耐性菌とは!?
抗生物質を使い続けていると、細菌の薬に対する抵抗力が高くなり、薬が効かなくなることがある。このように、薬への耐性を持った細菌のことを薬剤耐性菌という。

また、薬剤耐性は、耐性を持たない別の細菌に伝達され、その細菌も薬剤耐性化になり、次々に連鎖していくことがある。
薬剤耐性菌の被害により、日本でも年間8000人以上が命を落としている。(国立国際医療研究センター病院と国立感染症研究所の研究グループが公表)
2019年12月に同センターが発表したプレスリリースによると、薬剤耐性菌の中でも頻度が高い「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)」と「フルオロキノロン耐性大腸菌(FQREC)」による「菌血症(細菌が血液に入り込んで起こる病気)」の全国の死亡数を厚生労働省のデータをもとに推計したところ、2017年のMRSAの死亡数は4224名、FQRECの死亡数は3915名と推計された。
さらに米国では、年間280万人以上が薬剤耐性感染症に罹患し、3万5000人以上が死亡しており、欧州でも薬剤耐性感染症によって年間3万3000人が死亡している。
経済学者ジム・オニール氏が2019年に調べた結果でも、 抗菌薬耐性は「2050年までにがんを抜いて世界一の死因になる」と言われている。
なぜ、抗生物質では殺せない細菌が増え、多くの人の命を奪うようになったのか。
それは、必要以上に抗生物質が使われてきたからである。
抗生物質を使うと細菌は大量に死ぬが、一部にその成分が細胞質内に入るのを防いだり、無毒化したりする能力を獲得した細菌が現れる。
抗生物質をやたらに使うと、抗生物質に弱い菌は死に絶えるが、強い菌だけが生き残り、耐性菌ばかりが増えてしまう。
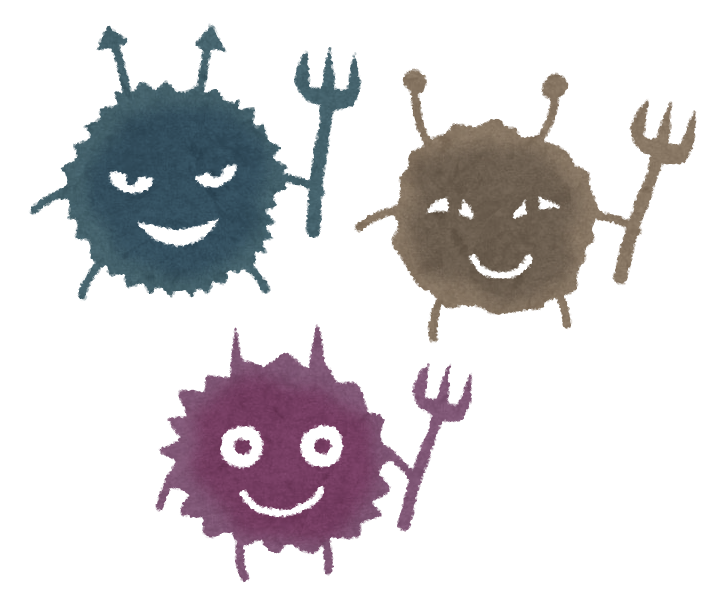
なぜ抗生物質の乱用が続いてきたのか。それは、本来は必要ないにもかかわらず、「念のため」という理由で処方されることが多かったからである。
風邪に抗生物質は効かない。風邪は細菌ではなくウイルスによる感染症なので、抗生物質では治せない。
国内の外来診療で出された抗菌薬(抗生物質)の6割近くが、効果がない風邪などウイルス性の感染症への不必要な処方だったことが、自治医科大などの研究チームの調査でわかった。
しかし、風邪をこじらせて細菌による感染症を起こしては大変と、念のための抗生物質がしばしば処方されてきた。抗生物質の乱用が蔓延してきたのである。
2019年11月、東京大学医科学研究所の研究グループが、ゾフルーザを投与された38人を対象に調べたところ、9人に耐性ウイルスが検出されたと発表した。
とくに15歳以下の小児で頻度が高く、約3割が耐性化していた。この耐性ウイルスが蔓延するかどうかは今のところわからないし、すぐに問題にはならないかもしれない。

しかし、問題は新型インフルエンザなどの爆発的流行(パンデミック)が起こった場合である。実は、これに備えて国家備蓄されているタミフルでも、すでに耐性ウイルスが見つかっている。
もし、いざというときに「効く薬がない」となると、パンデミックが起こった時には、まっさきに抵抗力の弱いお年寄りや乳幼児、重病人などが犠牲となる可能性がある。
その人に薬が必要かどうかを見極め、抗菌薬の適正使用の徹底が医師に求められる。
また今後は、医師が治療に使う際の薬の選択の基準や新薬開発の在り方などを議論する必要がある。
製薬企業には、薬剤耐性菌に対する新たな抗菌薬の開発が求められる。薬剤耐性菌との戦いには、新たな抗菌薬の開発が欠かせない。

しかし、社会的なニーズは高い反面、収益性は低く、製薬企業としてもなかなか取り組みづらい抗菌薬の研究開発となっている。
抗菌薬の開発には非常にコストが掛かり、1つの抗菌薬を開発するのにおよそ10億ドル掛かると言われる。
また、日本では耐性菌による感染症自体が少なく、臨床試験を行うのも簡単ではない。
日本製薬工業協会も厚生労働省に対して、薬剤耐性対策のための新薬開発の促進策を提言。
新規抗菌薬を国が買い取って備蓄する制度の導入や、産官学の連携による基金と研究開発コンソーシアムの設立、開発に対する報奨制度の創設などを提案している。
創薬促進検討委員会の委員長を努める舘田氏は、「耐性菌との戦いは、学会だけではできないし、行政だけでもできない。企業や一般市民を巻き込んだ活動として広げていかなければならない」と語っている。


